音読で得られる効果とは?学力向上が期待できる音読のポイントを押さえよう
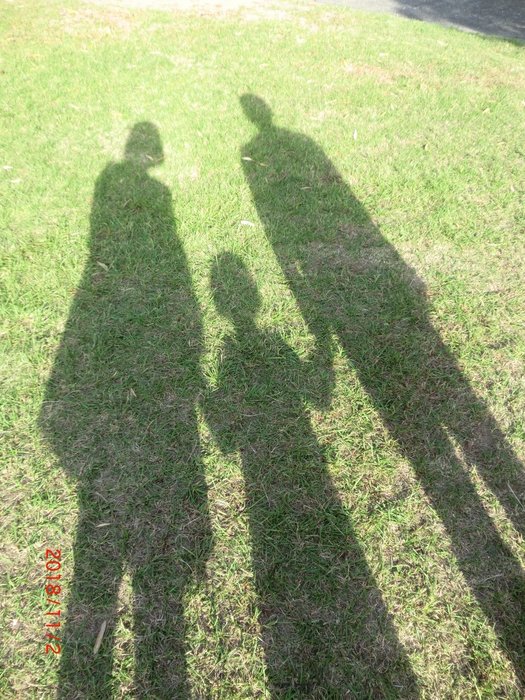
音読が宿題となる理由
国語の宿題で出される音読は、なぜ家で毎日取り組む必要があるのか気になる方もいるのではないでしょうか。実は毎日の音読にはきちんと意味があるのです。 その理由をいくつかご紹介しましょう。
授業の理解を促すため
学校の授業では1つの物語について学習する時間に限りがあるため、正しく文章が読めていることが前提で授業が進んでいきます。授業の音読練習だけでは内容を理解するのが不十分という理由から、自宅で音読をして物語の構成や展開をきちんと理解してもらおう狙いがあります。
読解力を高めるため
子どもの学力の基礎となる読解力とは、文章を読む力のことです。他にも文章の意味をきちんと理解し、自分なりの解釈や気持ちを言葉にする力も含んでいます。
読解力は国語だけではなく全教科に必要で、特に算数や英語、理科などは読解力がなければ解けない問題も多いのです。学習効果の土台となる読解力をつけるために音読を行っているともいえるでしょう。
大きな声で読む練習をするため
小学生になると皆の前で発表をする機会が増えます。発表をする時は、クラス全員に聞こえるようにはっきりと大きな声で話さなければなりません。また、会話とは違う抑揚をつけた話し方も必要です。音読の練習で活舌よくしっかり声を出せるようになると、自信をもって人前で発表ができるようになってくるでしょう。
テンポよく話をするため
声に出して文章を読むと、どこで区切れば話しやすくなるのか、言葉の意味や流れを意識できるようになります。音読を継続していると、日本語のテンポやリズムが自然に身についてきて、テンポよく話せるようになるでしょう。
音読と朗読の違いは?声に出して読むのは同じでも目的が異なる
音読と朗読は声に出して文章を読むという点は同じですが、それぞれ目的は違います。朗読は聴いている相手に物語の本質を伝えることが目的で、抑揚をつけたり感情を込めたりするのが特徴です。それに対して音読は、自分自身のために行うもので、感情を込めるのではなく正しく読めているかが重要になります。
音読による学習効果にはどんなものがある?
音読を毎日続けると、脳に刺激が与えられ学習効果を上げるそうです。その学習効果について、詳しくご紹介していきます。
読解力や語彙力がつく
音読は、文章の流れや切れ目を考えて読むことが必要となるため、自然に読解力がついてきます。黙読と違い、音読では知らない単語につまずいた時に文章を読み飛ばせないため、言葉の読み方や意味をきちんと調べるようになります。その結果自然と語彙力がアップするのです。
大人でも、「取扱説明書を読んでも内容が分からなかったのに、声に出してみたら理解できた!」という経験がある方がいるのではないでしょうか。子どもも同様に、黙読で文章の内容を理解するのが難しくても、音読だと内容をイメージしやすくなります。
暗記力や記憶力の向上
音読をすると、脳の前頭前野と呼ばれる部分が活性化していき、記憶力が良くなると言われています。前頭前野は思考や記憶などを司る部分です。目から入れた情報を、声に出して耳で音声として認識するため、黙読よりも脳が複雑に作業します。広範囲で脳が活性化することで、暗記力や記憶力の向上が期待できるのです。
集中力がアップする
音読中は声を出して読むことに集中します。頭の中で他のことを考える余裕がなくなるため集中力がアップするようです。音読を続けると少しずつ周りに気をとられることがなくなってくるでしょう。子どもが学校から戻って勉強や宿題に集中できない時は、子どもに「音読から始めてみようね」とすすめてみるとよいでしょう。
コミュニケーション力の向上
脳の前頭前野は、感情の抑制や行動の制限をする働きがあります。音読で前頭前野を活性化すると、自制心や自主性が向上してコミュニケーション能力を高める効果が期待できます。
ストレス解消にもなる
音読で脳の前頭前野を刺激すると、気持ちを落ち着かせる作用のあるセロトニンが分泌されます。セロトニンが分泌されると、自律神経のバランスが整い気持ちが落ち着くためストレス解消につながります。
速く黙読ができるようになる
音読で語彙力や読解力が高まると、文章を理解するスピードが上がり黙読が速くなります。黙読スピードが速くなって読解力が高まれば、限られた時間で問題を解くテストの時など問題の理解が速くなり、余裕をもって問題を解くことができますね。
やる気が高まる
音読をすると作業興奮が生まれ、やる気が出ると言われています。作業興奮とは、始めるまでに面倒くささを感じていても一度作業を始めたら意欲や集中力が湧いてくることで、ドイツの精神科医エミール・クレペリンが提唱した概念です。
年末の大掃除をやろうと子どもに声をかけて手伝うまでに時間がかかっても、いざ始めてみると集中して取り組んでいた、という例えが分かりやすいでしょう。
行動を始めてからやる気が出るまでの時間は、だいたい5~10分と言われています。子どもが勉強に気分が乗らない時などは、問題を解くような教科の前にまずは音読をしてみることで、勉強にやる気が出るかもしれません。
音読をする時に大人が注意すること
音読による学習効果をさらに高めるには、親の対応も重要になります。ここでは、子どもが宿題で音読をする際に親が注意するポイントをまとめましたのでご紹介します。
「ながら」で聴かない
子どもが音読をしている時に、家事をしながら聴いてしまう方は多いのではないでしょうか。ここは、なるべく手をとめて「聴いている」姿勢を見せることが大切です。きちんと聴いてもらえることでモチベーションが上がり、安心感を与えます。
上手に読めなくても叱らない
子どもが音読をしている時に「違うよ」や「声が小さいよ」など指摘すると子どもはプレッシャーとなり失敗を恐れるようになります。基本的には間違えていても見守り、子どものペースを大切にしてあげると音読が楽しくなり、学習効果も高まるでしょう。
読み終えたら褒めてあげる
音読の宿題を終えたら、声の大きさ、読む速さ、読む姿勢、間違えに気づけたか、句読点に気をつけたかなど、どこか1つ良かったところを褒めてあげるとよいでしょう。「大きな声で読めたね」「間違えずに上手に読めたよ」など褒めてもらえると自信がついて音読が好きになるかもしれません。
内容を質問してみる
音読が終わったら、内容について質問をするとよいでしょう。物語の内容や、登場人物の気持ちなど質問してみることで子どもの理解度も知ることができます。一緒に内容を考えれば音読が楽しい時間となり、想像力や読解力も高まるでしょう。
学年別のおすすめ音読方法
音読は子どもの年齢や学年に合った方法があり、徐々に難易度を上げることでさらに効果的でしょう。学年別にご紹介します。
小学校低学年・中学年は日本語のリズムを身につける
小学校の低学年・中学年は頭が柔らかく、想像力も豊かです。しかしまだ読む力より聴く力の方が優位となる年齢。自分で読むよりも読み聞かせで物語を聴いた方が内容を理解しやすいため、音読で読む力を養っていく必要があります。
まずは日本語のリズムをつかむのに「名文音読」がよいでしょう。百人一首やかるたなど遊びを取り入れたものや、落語の寿限無などリズムの良いものは言葉の感覚を身につけやすいためおすすめです。
小学校高学年は新聞で知見を広げる
小学校高学年には、新聞の音読がおすすめです。新聞はコラムやニュースなどジャンルも多く社会に関心をもつきっかけにもなるでしょう。
朝刊の1分程度で読める記事を音読することから始めていき、毎日取り組むことがよいのではないでしょうか。中学受験を考えている場合には、時事問題のトレーニングにもなりますよ。
中学生はスピードを意識する
中学生におすすめしたいのが、スピード音読です。速い音読は通常の音読以上に脳が活性化されて、頭の回転速度が上がります。速さを意識して1日15分程度音読を続けると、前頭前野の体積が増えて、抑制力や想像力、記憶力、思考力が伸びると言われています。
小学生と比べ音読の機会が減る中学生は、ご家庭でスピード音読を習慣にするとよいですね。高校受験に向けてもよいトレーニングになりますね。夏目漱石の坊ちゃんなどテンポがよいものを選ぶと読みやすいでしょう。スピード音読のコツは、テンポよく抑揚をつけ3~4行を一息で読み、視線は読んでいる文字から3~4行先を見ることです。
さいごに
小学校入学すると始まる「音読」の効果についてご紹介しました。家事などで忙しいと、手を止めて宿題を見てあげるのはなかなか難しいこともありますよね。しかし、子どもは音読をきちんと聴いてもらえると、学習へのモチベーションが上がります。日々の音読を通じて、語彙が豊富になり、コミュニケーション能力も高くなるなどさまざまな学習効果が期待できますよ。
筆者の娘は小学1年生で、今年から音読が始まりました。全てひらがなだった文章に少しずつ漢字が増えてきたり、句読点に気をつけながら読んだりする様子に成長を感じます。頷きながら聴いているアピールすると娘もこちらを見ながら読み聞かせをするように読むことも!学力の基礎を養うためにも、親子一緒に楽しみながら音読に取り組めるといいですね。
参考サイト
- 株式会社Nogifa|作業興奮とは何か?|(https://zisou.net/blog/136#:~:text=%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E8%88%88%E5%A5%AE%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%81%E4%B8%80%E5%BA%A6,%E9%9B%86%E4%B8%AD%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82)
- 株式会社 致知出版社|齋藤孝の“頭の回転速度がUPする速音読”|(https://www.chichi.co.jp/web/%E9%BD%8B%E8%97%A4%E5%AD%9D%E3%81%AE%E9%A0%AD%E3%81%AE%E5%9B%9E%E8%BB%A2%E9%80%9F%E5%BA%A6%E3%81%8Cup%E3%81%99%E3%82%8B%E9%80%9F%E9%9F%B3%E8%AA%AD/#:~:text=%E9%80%9F%E9%9F%B3%E8%AA%AD%E3%81%AE%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E3%81%AF,%E3%81%8A%E3%81%A3%E3%81%97%E3%82%83%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82)
- 株式会社 伸芽会|子どもの読解力を高める~幼児期からとるべき対策 - 子育て&教育ひと言コラム - 伸芽’Sクラブ - 受験対応型託児所 -| (https://www.shinga-s-club.jp/column/%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%AE%E8%AA%AD%E8%A7%A3%E5%8A%9B%E3%82%92%E9%AB%98%E3%82%81%E3%82%8B%EF%BD%9E%E5%B9%BC%E5%85%90%E6%9C%9F%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%A8%E3%82%8B%E3%81%B9%E3%81%8D%E5%AF%BE/#:~:text=%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%20%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%AE%E8%AA%AD%E8%A7%A3%E5%8A%9B%E3%81%AF%E9%87%8D%E8%A6%81&text=%E8%AA%AD%E8%A7%A3%E5%8A%9B%E3%82%92%E9%AB%98%E3%82%81%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%A7%E5%AD%A6%E5%8A%9B%E5%90%91%E4%B8%8A%E3%81%AE%E5%8A%A9%E3%81%91,%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E9%87%8D%E8%A6%81%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82)







